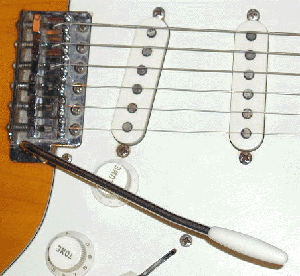いつもご覧いただきありがとうございます。
アームを使用する際、ブリッジをどう設定するかを前回は書きました。今回は
その意味を紹介します。
アームを使った奏法はまさしくエレキギターのみの奏法です。それ故に愛用されてきました。
当然とあるこの奏法は今思えば凄い発想ですね。しかし弱点もあります。チューニングの
狂いです。今回のシンクロナイズトトレモロ(以下トレモロ)はボディ側にはザグリ、いわゆるスペースは
ないものとします。そうするとアームの奏法はアームをダウンする、チューニングが下がる
奏法しかできません。そうでない場合もありますが今回は省きます。このアームダウンという奏法は
アームを使う一般的な奏法です。アームをダウンするとナットを通してペグの弦の巻きが緩みます。
そしてこの時点でナットの溝にある弦は100%で動きません。ペグの方向に滑るのですが必ず
アームダウンした分だけ滑る訳ではありません。アームダウンをした際、どうしてもこの2点の
状況になります。
一度緩んだ弦がもとに戻ることはありません。チューニングの際、ペグは本当に少ししか動かしません。
半周もすればもう音は全然違う音程になるはずです。ですのでアームダウンしてほんの少し弦が
緩み、元に戻らなければもう完全にチューニングは狂います。アームダウンにも限度はあります。
6点のねじで固定しているためそんなに大きくはできないのですがそれでもやはり大きく緩むことに
なります。
そしてナット。こちらも同様に滑り具合はバラバラです。
対処として、アームダウンをすればアームアップが必要になります。アームアップは音程を変えるだけ
でなくペグやナットで緩んだ弦を引っ張ることで元に戻そうとするアクションなのです。
(ただし、完璧に戻るわけでもありません)ですからアームを多用する場合は必ずブリッジの後方
を浮かせた状態にしておかないといけません。アームアップを可能な状態にするということになります。
アームの使用が可能なブリッジはまだあります。その一つにピグスピータイプがありますがこれは
かなり強引なものです。前回に紹介したチューンオーマチックに取り付けが可能ではあるのですが
ブリッジ側で弦が緩みますのでアームをアップしても大きくチューニングは狂います。
このようにアームはとても面白いものではあるのですがチューニングの安定を考えれば少し使うの
は躊躇します。その意味で絶対に必要かといわれれば疑問です。シンクロそのものは良いブリッジ
なのですがアームは設定に注意をしたいです。
次回はフロイドローズ式を紹介しようと思います。
よろしくお願いします。